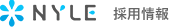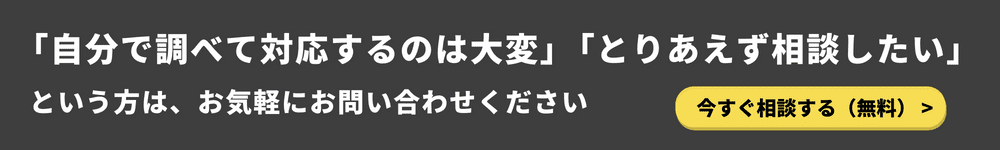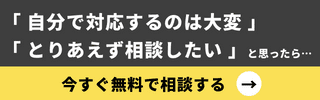【インタビュー】三井住友カード、「セミインハウス」によるサイト作成を実現。事業主とベンダが良好な関係を保つための「2つの愛」とは
三井住友カード株式会社(以下三井住友カード)は、「ゼロからはじめるクレジットカード」をはじめ、約3年のあいだに10のオウンドメディアを立ち上げ、運用しています。
主に、これらのサイト制作や運用は株式会社メンバーズが、集客施策やコンテンツ作成はナイルが手がけていますが、三井住友カードは自らも積極的に施策立案に携わる「セミインハウス」とも呼べる体制を構築しています。
デジタルマーケティングをインハウスで行うか、アウトソースで行うかという議論があるなか、三井住友カードはどのような意図で「セミインハウス」の体制を作ったのか、また、事業主側とベンダ側でどのような関係構築をしているのか。三井住友カード株式会社 福田保範氏と、株式会社メンバーズ 佐藤正啓氏、そしてナイルから矢内尚輝 に話を聞きました。

写真左:三井住友カード株式会社 福田保範氏
写真中央:ナイル株式会社 矢内尚輝氏
写真右:株式会社メンバーズ 佐藤正啓氏
ナイルでは事例ページをご覧の方向けの無料相談会、壁打ち会を実施しております。
背景等をお伝えいただくことで、最適な非公開事例のご案内も可能です。
お悩みや課題が明確でない、ふわっとした内容に思えるご相談でも大丈夫です。
押し売りや手抜きはありませんので、お気軽にご活用ください。
目次
自分たちも当事者として携わる「セミインハウス」という形
——三井住友カードのオウンドメディア制作において、SEO含むデジタルマーケティングのアウトソース化に至った背景についてお聞かせください。当初、インハウス化は検討されたのでしょうか?
三井住友カード株式会社 福田保範氏(以下、福田):検討はしたのですが、リソースとノウハウ蓄積の観点から難しいと判断しました。インハウス化には、高度な専門知識を持つメンバーを社内に確保せねばなりません。しかし、問い合わせ対応などの通常業務が多いなか、デジタルマーケティングに専念するのは現実的ではありません。さらにジョブローテーションもあるため、ノウハウを持つ人員がずっと同じ業務に携わることも困難です。社内にはインハウス化を求める声も多かったのですが、費用対効果などを示してアウトソース化へと話を進めていきました。

——アウトソース化にあたって、どのようなことを意識されて体制を構築されたのでしょうか。
福田:完全なアウトソースというより、どちらかと言えばインハウス寄り、言わば「セミインハウス」な体制を組んでいます。アウトソースは、業務の多くを外部に委託し、事業主側は最終的な決定のみを行うのが一般的です。そうではなく、方針決定や施策立案から当社が主体となって行い、代理店やベンダと共にPDCAを回すようにしています。
——外部に全て丸投げをするのではなく、自分たちも当事者として施策に関わっていくと。
福田:そうですね。事業主側がデジタルマーケティングに主体的に関わるためには、ある程度の専門知識と、自社サービスや商品に関する知識の両方が必要です。インハウスでは前者を極めることが負担となり、アウトソースでは後者の視点が欠けてしまう。セミインハウスが理想的な形ではないかと考えています。
\ 自社の課題に合った事例が知りたい方はお気軽にご連絡ください/
「アウトソースはスピードが落ちる」という誤解
——以前からWebコンテンツ制作をインハウス化する流れがありましたが、最近は三井住友カード様と同様に、インハウスに課題を感じられているお客様も多いのでしょうか?
株式会社メンバーズ 佐藤正啓氏(以下、佐藤):インハウスからアウトソースへの切り替え、またはアウトソースとの併用へシフトされるお客様は増えていますね。インハウスでのWeb制作は人材が固定され、業務が属人化しやすい傾向にあります。派遣社員を導入しても、スキルやマインドが不揃いなことが多く、結局教育コストがかかりますから。
ナイル株式会社 矢内尚輝氏(以下、矢内):デジタルマーケティングの人材が市場にそれほど多くないのもあるでしょうね。SEOに特化した人材ならなおさら。事業主側がデジタルマーケティングのエキスパートを自社内で揃えて完結させるのは、難易度・コストともにハードルが高い……と、さまざまなお客様で耳にしています。
——インハウス化を選ぶメリットは「社内コミュニケーションによるスピード感」があると思います。アウトソースを成功させるには、事業者側と外部ベンダとの連携が鍵になると思いますが、三井住友カード様のプロジェクトではどのように解消しているのでしょうか。
佐藤:リソースやノウハウなどの万全な体制が作れるのであれば、インハウスのほうがスピードが出ると思います。セミインハウスの体制構築にあたっては、インハウスの環境に劣らず、かつアウトソースの強みであるリソースの柔軟性も持たせた体制が作れるように心掛けています。

矢内:事業側と外部ベンダの連携でいえば、三井住友カード様は担当者のコミット度が非常に高いですね。他のクライアント様では、リソースの問題もあり担当者が様々なプロジェクトに横断して関わっていて、SEOのプロジェクトに十分にコミットできていないケースがありますが、三井住友カード様は、それぞれのプロジェクトへの担当者の集中度・コミット度が高く、確実にスピーディに各施策が進行していく印象があります。
佐藤:三井住友カード様から社内情報を展開いただけるのも大きいですよ。プロジェクトが始まる際には、どういう経緯でこのプロジェクトがあるのか、時間を割いて説明していただけるので、弊社としても施策の提案がしやすいんです。結局、「アウトソースはスピードが落ちる」という話は、やり方次第で回避できるのではないでしょうか。
福田:全くその通りで、アウトソースだから連携が遅れるというのは、最終的には事業主側の怠慢なんです。きちんと情報が連携できていなければ、アウトプットの質が担保できないのは当然のこと。もちろんそこには、忌憚なくコミュニケーションができる、良好な関係がベースとして必要だとは思います。
矢内:期初・期末の予算や、サービス・プロモーションの大きな方針など、まとめて僕たちベンダにインプットしてくれる機会があるのは、施策の文脈や、他のプロジェクトの動きなどを把握できますし、提案にも活かせるので、とても助かります。これだけ丁寧に情報共有していただけていると、こちらとしても「知らなかった」という言い訳は許されないので、緊張感を持ってプロジェクトに取り組むことができますね。
事業主とベンダの良好な関係を作る「2つの愛」
——今回の体制構築に当たって、福田様が「良好な関係」を築くために心がけていることはありますでしょうか。
福田:実は、前職ではベンダ側の人間として、デジタルマーケティングを担当していたんです。常駐先のひとつに私の「恩師」とも言える部長がいまして、その方から学んだのが「愛」でした。
——「愛」とは……?
福田:「会社に対する愛」と「チームに対する愛」の2つあります。前者は、結果を出すためには自社のサービスや商品を愛さねばならない、ということ。自信をもって「これはいい」と言えるサービスでないと、お客様に十分に訴求できません。その部長からは「たとえ納得してないサービスだとしても、好きなところを見つけて、しっかり伝える努力をしなさい」と教えられました。現職でも、他のどの社員よりも自社のサービスを調べて、ベンダには「うちはいいと思っているから伝えてほしい」「もっといいところがあったら指摘してほしい」と言うようにしています。
——「チームに対する愛」についてはいかがでしょうか。
福田:その「恩師」は、3ヶ月に1度、事業や方針について話す場を設けていたんです。そこには必ず代理店やベンダを集めていました。「お互いの案件を奪うという発想ではなく、ひとつのチームとして、クオリティが高いものを出してほしい」と。これには、各社の成果にきちんと対価を払うというのと、チームメンバーとして個人の成長を促すという2つの意味がありました。会社など関係なく、ひとつのチームとして、プロジェクトに入って成長できてよかったなと思ってほしい。私もその想いに共感し、意識しながら仕事しています。
——それは佐藤さんや矢内さんに対しても?
福田:2人が社会人に成り立てのころから仕事をしていますから、私が半分育てたと言っても過言ではないですね(笑) 声を荒げて怒るときもあるなど、私も恥ずかしい姿を見せてきました。2人に共通して好きなところは、言い返してくれるところなんです。「違う」と思ったときは気合いが入った顔になって、恐れずに議論してくれる。
佐藤:プロジェクトの成果に本気で向き合って、真摯に議論してくださるので、弊社としても中途半端な仕事はできないなと思うんです。成果を出す上で、おかしいと思った所はきちんと反論もします。福田さんは、固いやり取りが続いたあとにウィットに富んだ一言を入れられたりして、プロジェクトメンバーとの関係づくりについては自分も参考にしています。
矢内:クライアントの言うことを受身に唯々諾々に受けてしまうばかり…という代理店も見かけるのですが、それってやっぱり全然面白くないですし、パートナーとして能動的に「こうあるべき」という提案をするこだわりは持っていたいんです。なので、その場を変に収めるだけというようなコミュニケーションはやらないように、と常に心がけています。
 福田:全然いいんですよ。こちらも議論していて、すごく楽しいんです。私が100%正しいなんて絶対無いし、プロにお願いしているわけですから。あまり事業主側を上に見過ぎないというか、もっと代理店やベンダはプライドを表に出していいと考えています。
福田:全然いいんですよ。こちらも議論していて、すごく楽しいんです。私が100%正しいなんて絶対無いし、プロにお願いしているわけですから。あまり事業主側を上に見過ぎないというか、もっと代理店やベンダはプライドを表に出していいと考えています。
覚悟と時間、そして熱があるかどうか
——佐藤さんと矢内さんは、現在の体制ができあがるまでに苦労した点はありますか。
佐藤:各社間で用語・ルール認識にズレがあり、それをすり合わせるまで苦労しましたね。「校了」という言葉ひとつとっても、「原稿が納品されたタイミング」を指すのか、「事業者側のOKが出たタイミング」を指すのか、お互いに定義が食い違っていたんです。結果として連携がスムーズにいかず、手戻りや確認作業が発生してしまって。些細なことですが、積み重なると最終的に大きなトラブルにもなりかねません。言葉の定義や運用ルールを統一し、双方が同じ認識を持って仕事を進めていけるようにするため、ナイルさんと何度もミーティングして詰めていきましたね。
矢内:そうですね。立ち位置が異なるメンバーが連携するわけですから、ルール作りは非常に重要でした。また、メールや電話が主体だったやり取りから、Backlogを使って情報連携するようにブラッシュアップしていったのも、コミュニケーションコストの削減にはインパクトが大きかったです。
——事業主側からは、2社のあいだで認識の齟齬が生まれていることを把握されていましたか?
福田:もちろんです。考え方や文化がそれぞれ異なるのは、チームビルディングでも、それこそ友達同士でもあることなので、普通に起きうることと捉えていました。あまりに続くときは、私からうざったいメールを送ることもありましたが(笑) それも意図的なもので、嫌われ役は私1人でいいかなと思ってやっています。
——マニュアル作成が完了するまでは、どれくらいかかったのでしょうか。
福田:完成することはありません。現在も進行中です。できていないことはたくさんありますし、完成させようと思って仕事をしていないですね。
矢内:三井住友カード様は新しいチャレンジや取り組みに積極的なんです。新しい軸でメディアを作ったり、立ち上げ方を変えてみたり。
佐藤:新しいことを始めれば、それに伴って新しい問題も出てきます。問題が全て解決するということは、新しいことをやっていない、ということを意味するのではないでしょうか。
——最後に、社内にSEOの知見がある人材が全くいない場合、セミインハウスを実現するには何から始めるのがよいでしょうか。
福田:当事者として知識を持つ人間が不可欠なので、難しいですね。6ヶ月ほど外部の講師をアサインして社内に専門家を作り上げるか、それとも中途採用に力を入れて人材を確保するか……。いずれにせよ、インハウスやセミインハウスを実現するには、覚悟と時間、そして熱が必要だと思います。トップダウンでそれらを許容できる体制であることも欠かせないでしょうね。
編集後記
社外のSEOの専門家との連携は、社内コミュニケーションよりも時間がかかることが多く、挑戦を躊躇される方、現在苦戦している方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような企業さまにとって、今回の記事がSEOで成果を出すための組織づくりの参考になれば幸いです。福田さまがお話されていた「サービス」と「チーム」への愛は我々も、常に持ちながらプロジェクトに取り組ませていただきます。
福田さま、佐藤さま、お忙しい中ありがとうございました。
※取材はZoomで行い、撮影は緊急事態宣言解除後に行ったものです
SEOを始めとするWebマーケティングインハウス体制づくり(内製化)についてお悩みがありましたら、お気軽にナイルの無料相談をご利用ください。
お悩みや課題が明確に言語化されていなくても大丈夫です。
押し売りや手抜きはありませんので、施策のお悩みなどをお気軽にご相談ください。
自社でSEOに取り組みたいとお考えの方へ ナイルでは、SEO体制を貴社内に構築するSEO内製化・インハウスSEO支援が可能です。貴社の状況を把握し、段階的な支援を行うので、無理なくインハウスSEOを実現できます。サービス資料では内製化の流れや事例・実績、料金プラン例を紹介しています。SEO体制の悩みをプロに相談したい、見積もりが欲しいといった方は、お気軽に無料相談をお申し込みください!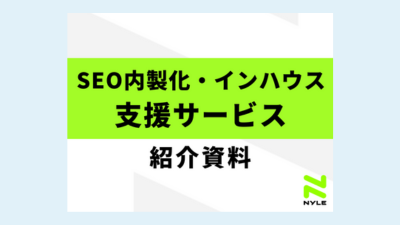
この記事もチェック
ナイル株式会社について
自社のWeb運用ノウハウやSEO技術を強みとし、コンテンツマーケティングや分析など、Webサイトの総合的なROIを改善コンサルティングを展開しています。Webサービスを得意とする企業ならではのコンサルティングで、企業様のWebビジネス成長を支援いたします。

取材・メディア掲載に関するお問い合わせは、こちらからお問い合わせください。